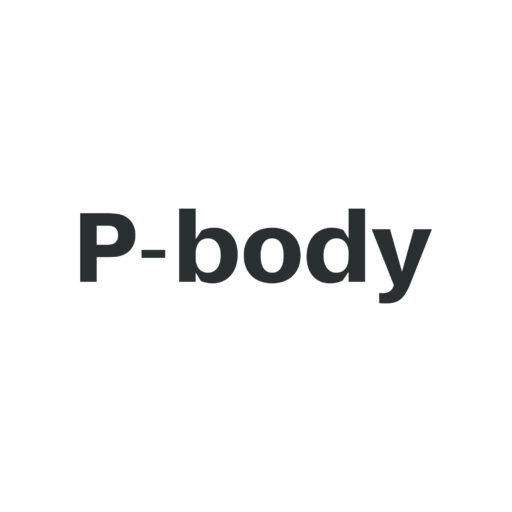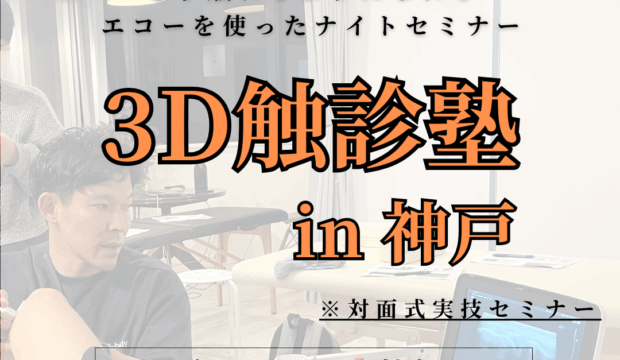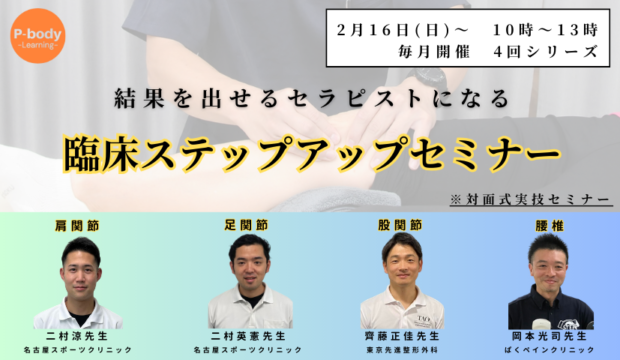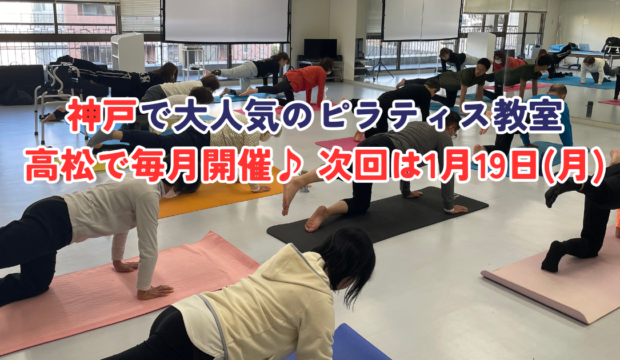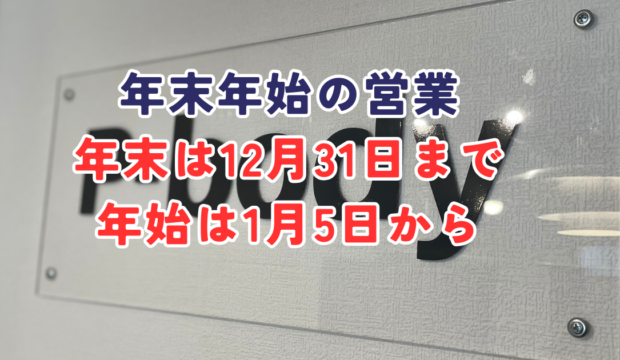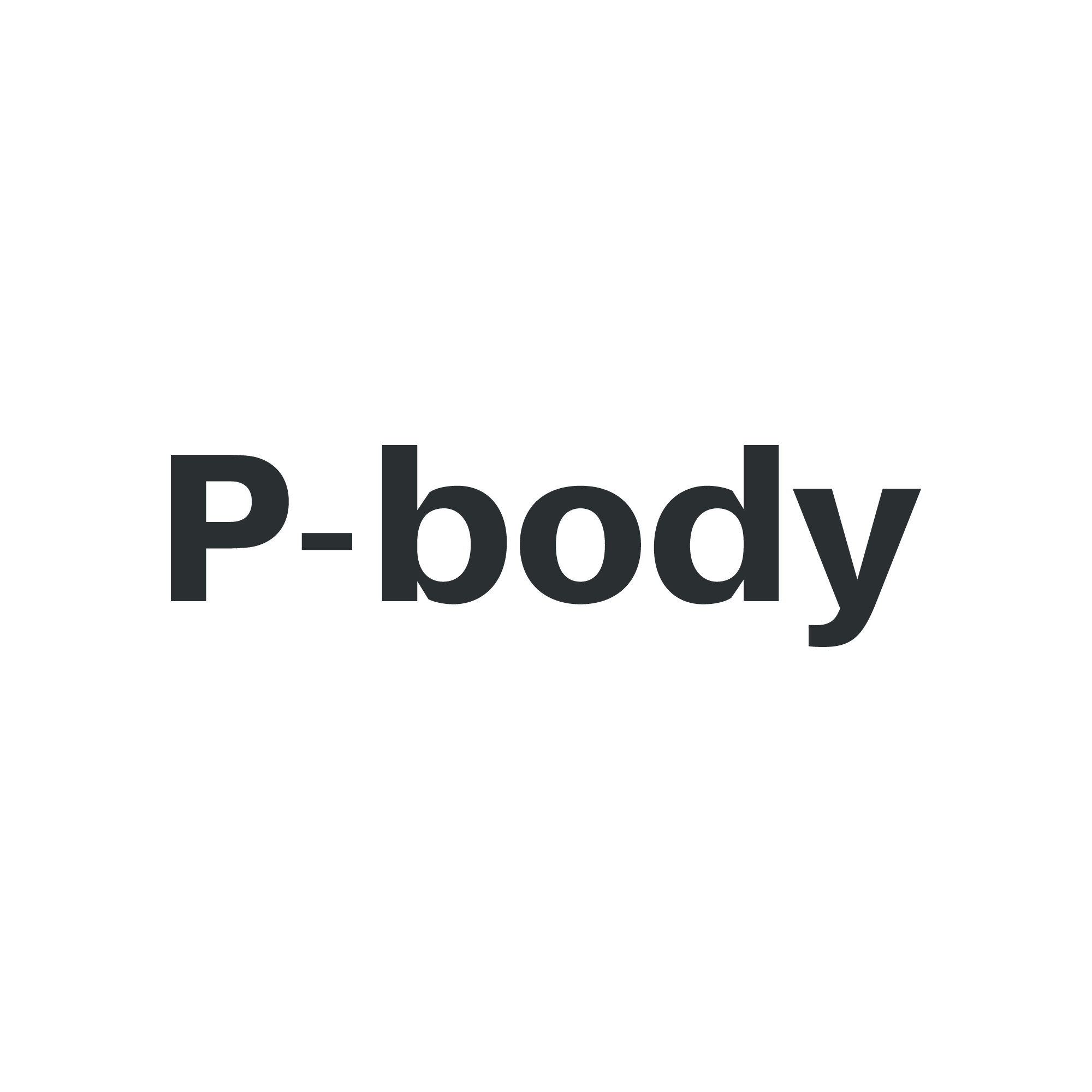こんにちは!
理学療法士のKです!
『最近走っているとすねがずっと痛い…』
『練習後に同じ場所の痛みが続いている…』
『歩いても痛くなってきた…』
ランナーやスポーツをされている方の中には、運動中や運動後に同じ場所に長く続く痛みを経験したことはるのではないでしょうか?
もしかしたらそれは疲労骨折をしているかもしれません…
この記事では、疲労骨折の病態や原因、治療方法などについて詳しく解説します。
疲労骨折とは

疲労骨折とは、骨の同じ部位に繰り返し加わる小さな力によって骨にひびが入ったり、ひびが進んで完全に骨折したりした状態のことをいいます。
1回の大きな力で骨が折れる通常の骨折とは異なります。
疲労骨折は骨への負荷が過度になり、骨が回復する十分な時間を与えられない場合に発生します。
なりやすい年齢
疲労骨折は、あらゆる年齢で発症しますが、骨や筋力の発育的な問題から、成長期に多くみられると言われています。
また、女性運動選手の3主徴(骨粗鬆症、無月経、摂食障害の徴候)で生じやすくなるとも言われています。
どこの骨に起こりやすい?
疲労骨折は、下肢の骨におこることが多く、すねの骨(脛骨)、すねの外側の細い骨(腓骨)、足の甲の骨(中足骨)などに多くみられます。
また野球では肘の骨やゴルフでは肋骨におこることもあります。
また成長期に多い腰椎分離症も腰椎の疲労骨折です。
疲労骨折の症状

疲労骨折は、以下のような症状がみられます。
局所的な痛み
最初は運動時・動作時のみに軽度な痛みを感じますが、運動中や負荷をかけたときに痛みが増すことがあります。
進行すると安静時にも痛みを生じるようになり、重度の場合は歩行が難しくなることもあります。
通常の骨折のように、皮下出血や激しい動作時痛を伴う事は少ないですが、局所の腫脹や圧痛がみられます。
腫れと炎症
骨折部位にはしばしば腫れや炎症が見られます。
患部を押すと痛みを感じることがあります。
炎症がある場合は患部を氷で冷やすようにしましょう。
疲労骨折の原因
なぜ疲労骨折は起こるのでしょうか?
疲労骨折は以下のような原因が考えられます。
過度な運動
ランニングやジャンプなど、骨に負荷をかけるスポーツや活動を過度に行うことが、疲労骨折の主な原因となります。
特に長時間のトレーニングや急激な運動量の増加はリスクを高めます。
不適切なトレーニング
適切なトレーニングの方法やフォームを無視することは、骨に過度の圧力をかける可能性があります。
正しいフォーム運動を行うことは、疲労骨折を予防するために大切です。
骨密度の低下
高齢者や女性など、骨密度が低い人は、疲労骨折のリスクが高くなります。
骨密度が低下すると骨が弱くなり、負荷に対する耐性が低下するためです。
疲労骨折の診断方法
疲労骨折の診断にはレントゲンやMRIなどの画像検査が必要です。
疲労骨折の中でも初期の場合はレントゲンでは診断がしづらくMRIを撮影しないと分からないこともあります。
運動中や運動後の痛みが続く場合は早めに医師へ相談しましょう。
どうやって治る?

安静
骨は自己修復する性質を持つため、一般的に軽症であれば、運動をやめて安静にすることでほとんどの症状が治癒します。
痛みがなくなった後、軽いトレーニングからスタート段階的に強度を上げていきます。
急激に練習を増やさず、少しずつ時間をかけて完全復帰をすることが大切です。
リハビリ
疲労骨折は一度治っても再発したり、別の部位に発生したりすることもあります。
骨折部位の負担軽減できるよう患部周囲の筋力や柔軟性を改善させたり、体幹や股関節周囲などの患部外のトレーニングをしたりすることが大切です
適切な栄養
骨の健康には適切な栄養が不可欠です。
カルシウムやビタミンDを摂取し、骨密度を向上させることが予防に役立ちます。
トレーニングプランの見直し
疲労骨折は一度治っても再発したら別の部位に発生することもあります。
疲労骨折を経験した選手は、トレーニング方法や量、運動フォームを見直し、負荷を適切に管理することが必要です。
疲労骨折は気づかないまま進行している事が大半です。
運動量を調整したり、コンディションを改善したりしながら患部の負担を軽減させていきましょう。
痛みが長く続く場合は早めに医師に相談をしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
記事監修 理学療法士 K
整形外科クリニックに勤務し肩、膝を中心に延べ9万人以上のリハビリを担当
サッカーチームにトレーナーとしても帯同中